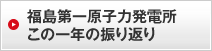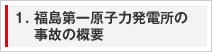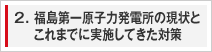地震発生日、現場では多くの作業が行われていました。平成23年3月11日14:46、地震が発生しました。揺れは長く続きました。所員が執務していた事務本館では天井のパネルは落下、棚は倒れて物が散乱しました。揺れが収まった後、免震重要棟脇の駐車場へ避難が行われました。ちょうど1週間程前に避難訓練を行ったばかりだったため避難は円滑に行われました。
ただちに、発電所全体の指揮をとる緊急時対策本部が免震重要棟という通常業務が行われる事務本館とは別の建物に置かれました。免震重要棟は、平成19年に発生した新潟県中越沖地震の教訓から建てられた免震構造の建物です。
15:27に津波第一波、15:35に第二波が到達。
発電の運転・監視を行っている中央制御室では警報表示や状態表示灯が点滅し、一斉に消えていきました(1、2号機)。

事務本館の状況(平成23年5月6日撮影)
設備復旧のため集まった所員(復旧班)は、照明の消えた中央制御室へ小型発電機と仮設照明を運び込み、計器類の復旧のために必要な図面を用意したり、協力企業からバッテリーやケーブルを収集したりしました。仮設照明設置後も照明が届かず真っ暗であったため、手持ちの懐中電灯の明かりを頼りに、配線図とケーブル番号の確認や配線の端末処理・接続作業を行いました。

写真23. 当直副長席で仮設照明を照らして対応
(報告書より)

写真24. 懐中電灯の明かりを頼りに指示値を確認
(平成23年3月23日撮影)
照明や計器の復旧によって発電所の状態を把握するための監視手段が少しずつ確保されていく一方、現場は依然として真っ暗であり限られた通信手段の中、余震・津波警報が継続する状況下での対応が続きました。
多くの社員が家族の安否確認が出来ない状況の中、当日勤務ではなかった社員も発電所に続々と駆けつけました。
<電源復旧作業>
重要な設備の復旧には、まず電源が必要です。事故直後から電源の復旧作業が鋭意行われました。原子炉注水のために重要な設備への電源の復旧が優先的に行われました。
電源盤近接での作業は暗所、水たまりの中、感電の恐怖がありました。また、足下に水たまりがある状態では作業を行うにも工具を下に置けないため、明かりを照らしたり道具を持ったりする人が必要でした。
11日深夜より当社および東北電力が派遣した電源車が発電所に到着し始め、電源車を用いた電源復旧作業が行われました。
その後外部電源復旧工事も開始され、29日までに全号機の中央制御室の照明が外部電源により復旧しました。

写真25. 中央制御室の照明復旧(4号機)
(平成23年3月29日撮影)
<格納容器ベント・注水作業>
中央制御室では、操作手順書を見ながら電源がない状況におけるベント操作手順の検討が行われました。11日の夜に原子炉建屋の線量が上昇したため、その後のベント作業に当たっては全面マスクを含め被ばくを防止するための装備一式、耐火服、セルフエアセット、APD、サーベイメータ、懐中電灯等が可能な限り集められました。現場は全くの暗闇のため1人では作業が困難であること、高線量が予測されること、余震で引き返すことなどを考慮して、2名1組の3班体制が敷かれました。また、通信手段がなく現場に行くと連絡が取れず緊急避難時の救出が出来ない恐れがあるため、1班ずつ現場に行き、中央制御室に戻ってから次の班が出発することとしました。現場に向かうメンバーの人選では若い運転員も自ら手を挙げましたが、放射線量が高く状況もわからない中へ若い運転員を行かせることが出来ないと考え、当直長、副長がそれぞれ割り振られるよう班が編成されました(1号機)。

写真26. セルフエアセット
(平成23年5月4日撮影)
作業環境は線量が高く蒸し暑く、照明がなく暗い中、懐中電灯の明かりだけが頼りという厳しいものでした。運転員がベント弁の開閉状態を確認するために足をかけたところ、熱くて履いていた長靴が溶けることもありました(3号機)。
1号機は12日の14:30頃、3号機は13日の9:20頃、原子炉圧力の低下が確認され、格納容器ベントが成功したと判断されました。1号機と3号機では格納容器の圧力が低下したことが確認され「格納容器ベント」は成功したと判断していますが、2号機については「格納容器ベント」による格納容器の圧力の低下は確認されていません。

写真27. ベント弁確認作業イメージ
(平成23年12月1日撮影)
※オレンジの部分に足をかけた際に長靴が溶けた。
一方、発電所の運転員は原子炉への代替注水ラインを構成するために、ベント操作と同様の厳しい環境の中、電動弁を手動で開けたりする作業を進めていました。
原子炉への注水は、建屋外部から消防車によって行いました。消防車は中越沖地震の教訓を生かして自衛消防のため配備されていたものでしたが、原子炉への注水のために臨機の対応として用いられました。
12日15:36、1号機で爆発が起きました。注水を続けていた社員と協力企業作業員は、消防車へ燃料を補給するため車外にいたところ、衝撃を感じてその場にしゃがみ込みました。空を見ると瓦礫が空一面に広がり、バラバラと降ってきました。近くにあった建屋脇のタンクの壁際で瓦礫をよけました。その場で立てなくなった作業員を周りが支え合いながら歩いて逃げました。
14日に3号機、15日に4号機の原子炉建屋上部が爆発しましたが、その後、原子炉注水用ホースの壊れた部分を布設し直すなどの作業が進み、再び原子炉へ注水を行えるようになりました。
また、使用済燃料プールについては、初めは自衛隊のヘリコプターを用いた水の投下や高圧放水車などによる放水が行われましたが、22日には4号機の使用済燃料プールに対し、初めて位置を確認しながらコンクリートポンプ車を用いた注水ができるようになりました。

写真28. 爆発後の1号機原子炉建屋
(平成23年3月12日撮影)

写真29. 爆風により窓ガラスが割れた事務本館
(平成23年3月19日撮影)